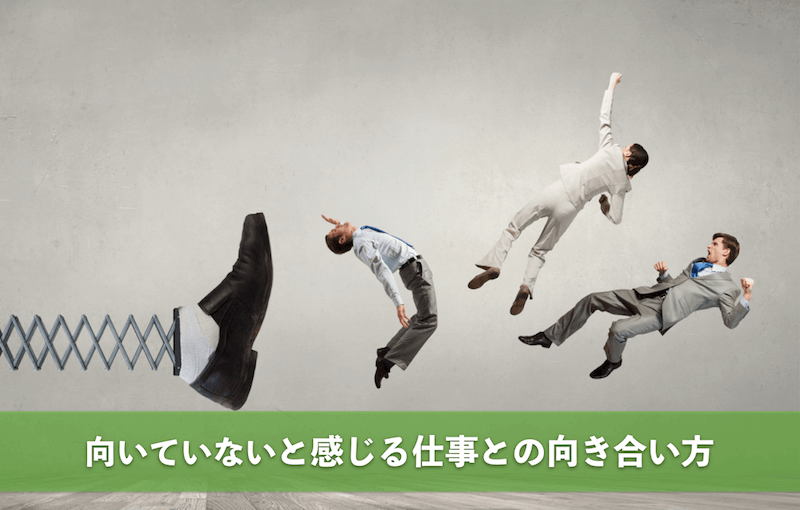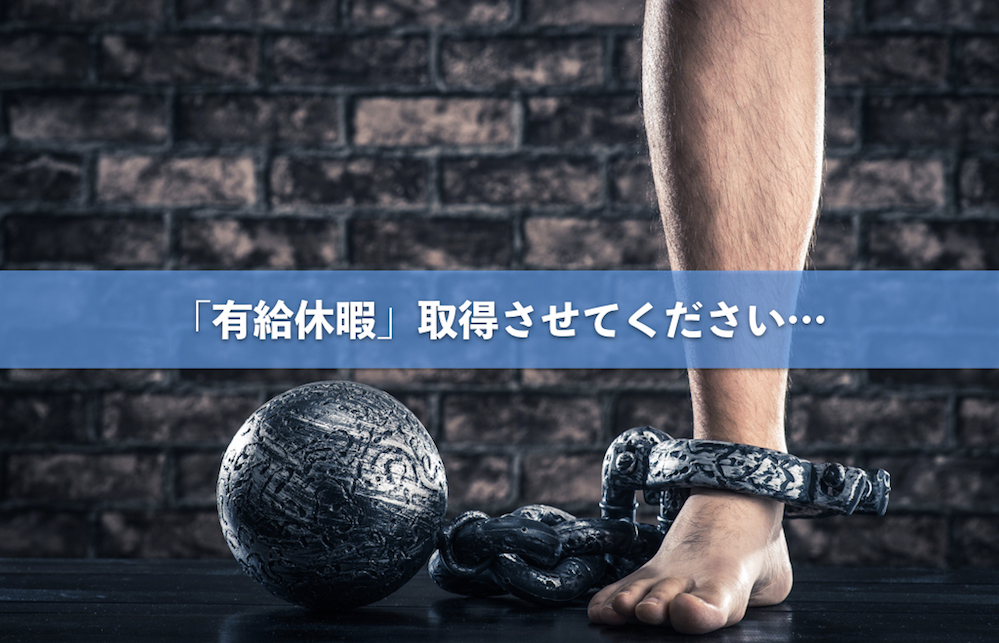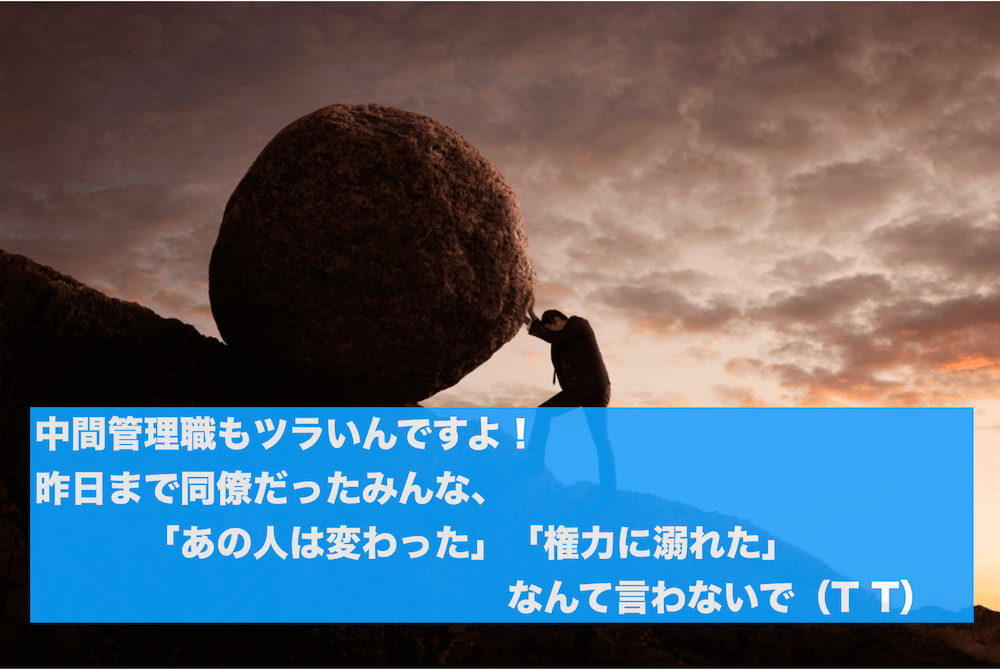
※このページにはPR広告を含みます
中間管理職の板挟み問題。どう解決するかは自分次第?!
あなたは、まさに中間管理職になったばかりか、なかなか管理職としての役割を把握できずに悩んでいる時期ではないでしょうか?
管理職になりたてのいわゆる「中間管理職」は、部長や課長といった上司や、今まで後輩として接してきた歳の近い部下を抱え始めて上下から板挟みにあうケースが多くなります。
近年では中間管理職という立場を望まずに、平社員で終わりたいという人も増えてはいますが、会社でのし上がって行くには確実に通らなければならない道。
ここでは、中間管理職が抱えやすい板挟みなどのストレスに負けずに役割をまっとうしていくための方法を紹介していきます。
管理職層の転職、および管理職への転職を希望する人の場合は、一般職の転職活動に加えて2つのハードルが発生します。ここでは、スキルや経験だけでは転職成功が難しい「管理職の転職」について詳細を説明します。
そもそも「中間管理職」ってどういう意味?
上から下から板挟み。ストレスの要因には何がある?
うまくストレスと向き合いながら職務責任をまっとうする方法
女性管理職にも活躍の場は拡がっている
有名漫画のスピンオフで中間管理職について学べるらしい
中間管理職は大変さばかりじゃない!
中間管理職とは?
管理職は労働現場において労働者を指揮し組織の運営に当たる者ですが、中間管理職はその管理職の中で自身より更に上位の管理職の指揮下に配属されています。
一般的には、課長や係長が中間管理職と呼ばれます。中間管理職には、管轄する組織やグループの成果の維持はもちろん、向上させるという役割があります。
また、会社の理念の翻訳を行い、部下に共有するという使命もあるのです。会社の存在意義を示す「企業理念」や、会社の方向性を示す「経営理念」を、中間管理職は行動指針や達成目標として部下に示します。
こうすることで、社員は経営者の打ち出す方向性を理解して実行に繋げることができます。これが「理念の翻訳」という役割です。ここまでの事を意識するのは最初は難しいでしょうが、必ず管理職研修などで教えられる事です。
名ばかり管理職という問題
管理職関連で問題となっているのは、名ばかり管理職です。「名ばかり管理職」とは、十分な職務権限を持たないにも関わらず、肩書きだけを与えられて管理職とみなされた従業員を指します。
ただ、多くの場合、残業代を支払われないという問題点があります。このグレーゾーンの問題は簡単にはクリアにはならないでしょう。
中間管理職がストレスを受けやすいケース5選
管理職層は一般社員とは違ったストレスを抱えるもの。上位の管理職層はある程度そのことを理解しているでしょうが、部下にはなかなか伝わりません。
「あの人は変わった」「あんなこという人じゃなかった」など、受け入れがたい部下にはいろいろと言われてストレスに感じているかもしれません。
ここでは、中間管理職がストレスを受けやすい事例を5つ紹介します。当然これ以外にもありますが、自分がストレスを抱えていないか?ということはセルフチェックも行いましょう!
【1】上司の指示に逆らえない
中間管理職の悩ましい状況の一つが、すぐ上に自分を管理する管理職がいることです。当然ですが、上司からは様々な業務指示を受けます。
上司から管理職という事実を利用され、管理職になったからこれぐらいできると言われながら、資料作成やトラブル対応など面倒なことを押し付けられたり、管理職にしかできない細かい雑務をやらされたりする事もあります。
管理職になったことを指摘されると反論しづらいことや、上司に良いように使われているという事実に絶望することが、ストレスに繋がりやすいとされています。
【2】部下がいうことを聞いてくれない
中間管理職は、部下のマネジメントも重要な役割ですが、こうしたマネジメントはストレスの原因に繋がることがあります。
とくに、能力が低い、もしくは消極的な部下やスタッフが管理対象となる場合には負荷が増えます。能力が低い場合には育てる必要がありますし、仕事に対して消極的な場合はやる気を出させる必要があるからです。
ただ、多くの人が経験したように人を変えるということは難しく、どちらも容易ではありません。
それでも組織としての結果を出していくためには、マネジメントを行う必要があります。そういったメンバーを除外して進めるわけにはいかないのです。
今まで以上に、部下に結果を出してもらわなければ成果が出せないので、こういった足止めは大きなストレスとなります。
【3】部下が起こした問題であっても責任を取らなければならない
中間管理職には、部下の犯したミスやトラブルの最終的な責任を取るという役割があります。
大きなミスや、部署の中だけで納まらないようなトラブルは上司が責任を取らされます。自分で起こしたミスやトラブルではない場合は、納得できないという感情が生じ、より強くストレスを感じてしまうでしょう。
しかし、それが中間管理職にとって業務の一部。トラブルが発生しないように、日々部下とコミュニケーションを取りながら仕事をチェックすることはもちろん、組織としてレベルアップできるような取り組みを行う必要があります。
【4】休日出勤は当たり前!残業代もつかない?
管理職あるあるですが、トラブルが起きた場合や、社内での定例報告資料の作成など休日出勤もザラにあります。それは、前述の「責任」の範囲に該当するからです。
管理職は一般職と違って、会議への召集頻度が上がります。自分の部署はもちろんですが、他部署との連携、また業務以外の定例会議などでほぼ時間を取られてしまうからです。
残業代が出ないのはおかしい?
管理職だから休日出勤の費用や残業代が出ないというのは、かなりグレーゾーンの話です。『労働基準法41条2項』では、管理監督者には割増賃金の支払は適用外となっています。
しかし、中間管理職とはいえ会社ごとに就業規則などでその役割の範疇はもちろん、どういった立場かを明記されている場合があります。
自分が会社においてどの立場かを明確にしておき、不当な扱いと感じる場合には弁護士などへの相談が必要でしょう。
【5】平社員の時と比べて明らかに責任が重くなってくる。
中間管理職は、部下のマネジメントだけではなく報告書や進捗状況確認書などの書類の作成、上司からの圧力など、下からも上からも板挟みされる立場にあります。
また、管轄する組織やグループのパフォーマンスを維持・向上させるという役割や、部下の犯したミスやトラブルの最終的な責任を取るという中間管理職の役目が決められています。
平社員にはこれらが無いので、管理職の組織運営は平社員よりも重い責任があるように感じられます。
中間管理職がストレスを乗り越えて役割を全うする心得5選
板挟みストレスが多い中間管理職層ですが、期待される役割は一般職よりはるかに高くなっています。その役割をまっとうするために必要な心得を5つ紹介します。
【1】上司の指示や会社の方針をしっかり咀嚼する
中間管理職は、会社の方針や理念を翻訳し行動指針や達成目標として社員に示す役割があります。また、管理職の立場としての上司からの指示や命令は多くなります。
こうした様々な状況に判断するのはストレスに繋がります。組織の人間はそれぞれに価値観や優先度を持っていますが、全てを完璧にこなすことは不可能です。
中間管理職の仕事は、状況に応じて判断を行い、説明・交渉しながら組織を正しい方向に向かわせることが必要です。「利益」や「社会貢献」など、会社の理念としてどういった指針で仕事を行なっていくのかを念頭に、本当になすべき仕事に集中する必要があるのです。
【2】部下とのコミュニケーション時間をしっかり確保する
部下のマネジメントは、中間管理職の役割の1つです。部下との信頼関係は、仕事をするうえで重要な繋がりだといえます。そのために必要なのは、各社員と仕事を通して達成したいことを一緒に考え、その目標と企業の方向性との接点を発見することです。
この接点を認識することで、社員は努力することで達成感を感じることができ、同時に自分が会社に必要とされていることを実感できるようになります。このように、会社に対するロイヤリティを上げて頑張ろうという気持ちを与えることは、部下のマネジメントの1つとなります。
「この前の資料良かったよ」「報告ありがとう」など、相手を褒める軽いひと言を挟めるようになると、場の雰囲気も良くなります。雰囲気づくりにも気を使ってみてください。
【3】プレイヤーは卒業!部下に権限を与える
中間管理職のミッションとして、チームとして成果を出すということがあります。自分が偉いという考えは持たず、部下1人1人と向き合って得意分野や方向性を把握する必要があります。
例えば、忙しい状況であっても、部下が話しかけづらいオーラを出してはいけません。そうすることで「報連相」などの連携を壊してしまう可能性があるからです。余裕ができた時に改めて話すなど、自分も相手に関心を持っていることを示すことが大切です。
また、とくに重要なのは、いつまでもプレイヤー気取りで仕事をしないことです。あなたの仕事はあくまで管理・誘導です。
プレイヤーとして優秀だったかもしれませんが、いつまでも自分でやっていると部下も面白くありません。また、チームとしても個々のレベルを上げていかないと、成果が上がりにくいのです。
部下に権限を与えて、今までよりも高いレベルの仕事を任せることも管理職の仕事であることを忘れないようにしましょう。
【4】今までとは違う!「ハラスメント」についてしっかり把握する
ハラスメントは、人を困らせることやいやがらせを指す言葉です。「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」「アルハラ」と、今では様々な「ハラスメント」があります。
定義としては、他者に対する言動等が本人の意図には関係なく、相手を不快にさせたり、尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えることを指します。
中間管理職では、上司と部下の板挟みでストレスが溜まりやすいため、発散を部下に当ててハラスメントを行ってしまうこともあります。また、自分の思うように部下が動いてくれない時など、ついついイライラして厳しい言葉を浴びせたりしてしまうこともあります。
しかし、一度ハラスメントを行うと信頼は一気に失墜します。自分の立場を考えて、グッと飲み込みましょう。
相手の受け止め方にもよる難しい問題ではありませんが、「どこまで言っていいのか?」ということは、相手との関係性の濃さでわかってきます。
ハラスメントを防ぐためにも、普段から部下とコミュニケーションをとって、その人のことを詳しく知るようにしましょう。
【5】人にばかり気を使わない。自分の癒しの時間を持つ
ストレスを乗り越えるためには、上司や部下など自分以外のことばかり気にするのではなく、自分自身の時間を確保することが重要です。
自分の時間では、運動や睡眠をするべきです。ジョギングやウォーキングなどの運動は、体が持っている免疫力や自律神経を回復させる機能を復活させます。
また、睡眠は体を休めて疲れを取ることができるのはもちろん、ストレスの軽減にも効果があります。
他にも、筋トレや自分がしたいことをするなどがありますが、こうした時間を持つことで心に余裕を取り戻すことができ、管理職としての役割を果たそうという意欲がまた湧いてきます。
女性の中間管理職も増えている。女性がさらに活躍するには?
中間管理職は、男性だけではなく女性も就くことができます。男性には無く女性にはある要素や、女性リーダーが持つ特徴を述べながら、女性でも中間管理職として活躍するための方法を考えます。
女性にある要素として社内コミュニケーションが得意というのがあります。女性は、縦社会の住人ではなく、縦横自由な社会で生きています。
縦社会では上を立てたり上の意見を尊重したりする流れがありますが、女性は会社のことを考え、自分の意見をシンプルにまっすぐに伝えたり、誰に対してもフラットで公正に話をすることができます。
男性では恐れ多いと感じやすい経営者や役員や、自分より上の立場の人、他部署の人、部下に対しても、女性は率直に話をできる方が多く、信頼されやすいです。
女性が活躍するには、これらを認識し仕事をすることが望まれるでしょう。
漫画『中間管理職 トネガワ』から学べること
『中間管理職 トネガワ』は『賭博黙示録カイジ』の登場人物の1人・利根川幸雄を主人公としたスピンオフ作品です。この作品は、中間管理職の利根川幸雄の苦悩と葛藤が描かれています。
利根川は、大勢の黒服部下をまとめる幹部でありながら、会長のご機嫌を最も身近で気にする立場であるため、現代社会の中間管理職に類似しており学ぶことが多いです。(まあ、普通では無いですけど)
カイジ本編で凶悪な敵であった利根川が、黒服で似た部下たちをマネジメントしながら信頼を得ようとして苦労する姿などに驚くと同時に、社会人の中間管理職のつらさがわかりやすく描かれているところが評価されています
中間管理職に疲れた…辞めて転職することはできるの?
中間管理職は出世した喜びはありますが、仕事に対する責任は大きく、上司からのプレッシャーはもちろん残業規制がなくなることによる長時間労働など苦労は多い立場です。
どうしても今の企業で管理職としての仕事に限界を感じた場合、転職をするという手もあります。ただ、管理職の場合は転職は難しいと言われる事もあります。その理由はいくつかあります。
- 管理職としてのポジションが少ない
- 年齢が高い
- 管理職から一般社員へのキャリアダウンを良しとしない風潮
しかし、昨今の人手不足の慢性化や経験豊富な中堅層への期待増などから、管理職経験者向けの求人が非常に増えており、30代はもちろん40歳以上の転職も活発化してきています。
管理職の転職には転職エージェントが確実
管理職の転職では、転生エージェントの活用は必須です。求人を探すなどの業務はエージェントに全て任せてください。
部下の管理や、会社の上位の仕事をしながら、自分で求人を探したり応募調整をすることは不可能です。時間と精神的な余裕がなさすぎます。
また、転職活動では管理職ゆえの問題もあります。それは、求人はかなり限られてくるということです。ですので、希望次第ではかなり企業数が絞られてしまいます。
失敗を重ねると、当然受けることができる企業も減少しますので、転職における「応募書類」や「面接」に関しては万全の体制を整える必要があります。そういったところを、転職エージェントにしっかりサポートを受けることが重要になってきます。
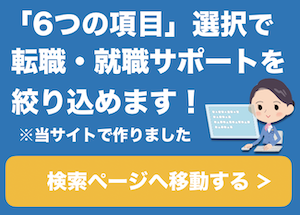 補足選択する6項目は「希望地域」「年齢」「性別」「雇用形態(現職と希望)」「希望職種」です。
補足選択する6項目は「希望地域」「年齢」「性別」「雇用形態(現職と希望)」「希望職種」です。
まとめ
「中間管理職」と聞くと響きが悪く聞こえますが、管理する側として今までとは違う仕事の楽しみ方もできるようになります。
チームリーダーやグループリーダーではできなかったような領域まで関わることができるようになるので、責任は重いですが、今までやりたくてもできなかったような案件に取り組むこともできます。
部署を横断するようなプロジェクトを立ち上げたり、部下を導いて困難を乗り切ったり、今までと違った目線で社会生活が見えるようになるでしょう。
負担は重いですが、あなたは独りではありません。今までと同じように、色々な失敗や先輩たちの経験から学んで社会に貢献していく気概で頑張りましょう。
管理職ではない人へ
最後に、まだ管理職ではない一般社員の方々にひと言。
周囲には「なんであの人が管理職なんだよ!」という人も少なからずいるでしょう。ただ、それ相応の責任をあなたの知らないところで負っている場合がほとんどです。
たまには「お疲れ様です」など励ましの言葉をかけるようにしましょう。人間関係は上下関係であっても重要です。一度相手の立場に立って物事を考えるようにしましょう。